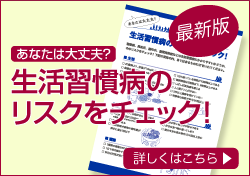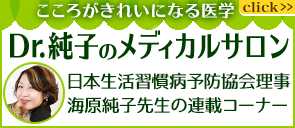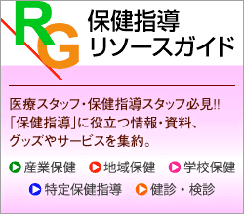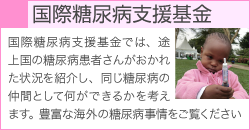高血圧
どんな病気?
高血圧は血圧の高い状態が続く病気です。
血圧とは、血管の中を血液が流れる際に、血管の壁にかかる圧力のことです。健康な人の血圧は、収縮期血圧(心臓が縮んで血液を送り出したときの血圧。最大血圧)が140mmHg未満、拡張期血圧(心臓が拡張したときの血圧。最小血圧)が90mmHg未満です。このいずれかが上回っている状態が、高血圧です。
血圧が高くても通常、特徴のある症状は現れません。症状が現れないのにもかかわらず、からだの中では知らず知らずのうちに、高血圧の悪影響がじわりじわりと広がっていきます。血圧が高いということは、血管の壁に強い圧力がかかっているということですから、それを治療せずにいると、血管が傷めつけられて動脈硬化が早く進んでしまうのです。言うまでもなく、血管は全身に張り巡らされていて、血管のない部分というのはほとんどありません。ですから高血圧の影響は全身に及びます。
とりわけ,脳や腎臓、目の網膜は高血圧の影響を受けやすいとされています。それに、血液を送り出す際に負担がかかる心臓も、高血圧の合併症が現れやすい臓器です。それぞれ、脳梗塞、腎不全、眼底出血、心不全などを引き起こします。そうならないよう、高血圧と言われたら、血圧が高くならないように、いつも気をつけておく必要があります。
●発見・診断の検査| 検査項目 | 解説 | |
|---|---|---|
| スクリーニング | 診察室血圧・家庭血圧 | 医療機関・健康診断や家庭での測定 |
| 詳しい検査 | レニン・アルドステロン等の血液検査。腎動脈超音波検査など腎機能検査(eGFR、尿蛋白など)、糖尿病検査(血糖検査)。心電図などの心臓検査など | 二次性高血圧の除外。危険因子、臓器合併症、脳心血管病などの予後影響因子の評価 |
検査はかかりつけ医で実施できます。そのほか、定期健康診断(職域)、特定健康診査、人間ドックでも行われます。
数字で見る高血圧
*高血圧治療ガイドライン2019
男性131.6mmHg、女性126.2mmHg
男性27.5%、女性22.5%
1,609万2,000人
高血圧の予防と治療
塩分をとり過ぎると血圧が高くなります。なぜかというと、塩分のとり過ぎは血液の塩分濃度を高めるように働きますが、ヒトのからだはそれを防ぐために、細胞の中の水分を血液に移行させて、血液の塩分濃度が上がらないようします。すると、血液の量が増えます。血液の量が多ければ多いほど、血管の壁には強い力がかかってしまう、つまり、血圧が高くなってしまいます。また、塩分のとり過ぎは、血管を収縮させるホルモンの反応を高めることでも、血圧を高くします。ですから、高血圧の予防・治療には、減塩が第一です。
また、太っている場合は減量が大切です。とくに内臓脂肪型肥満では腹腔内の脂肪組織から血圧を上げる成分がたくんさん分泌されてきます。ですから体重を適正にすると、血圧も正常に近付いてきます。そのうえ、糖尿病や脂質異常症(高脂血症)などの改善効果も得られます。これらの病気はすべて血管の障害を促す原因ですから、減量は血圧低下だけにとどまらず、多くの生活習慣病の予防・改善に有効的に働きます。
減塩や減量と同時に、からだを動かす習慣を身に付けることもお勧めします。からだを動かすことは、体重管理のうえでも必要ですが、それとともに血行を良くして血圧を下げる効果があります。ただ、血圧がかなり高い場合は、運動中に血圧が高くなり過ぎる可能性もあるので、無理は禁物です。
このほか、アルコールの飲み過ぎに注意しましょう。
薬物治療者での降圧目標は、75歳未満の場合は医療機関では最高血圧130未満かつ最低血圧80未満、家庭血圧では最高血圧125未満かつ最低血圧75未満。75歳以上の場合は、医療機関では最高血圧140未満かつ最低血圧90未満、家庭血圧では最高血圧135未満かつ最低血圧85未満です。
関連する生活習慣病
★の数が多いほど関連が強いことを意味します。
-
★★★
- これらの病気の最大の危険因子が高血圧です。
-
★★★
- これらの病気の重要な危険因子の一つとして高血圧が該当します。
-
★☆☆
- これらの病気は高血圧の患者さんが併発しやすく、また併発した場合は合併症が起こりやすくなります。
さらに詳しく
- 高血圧症(e-ヘルスネット、厚生労働省)
2015年12月 公開
2024年10月 更新