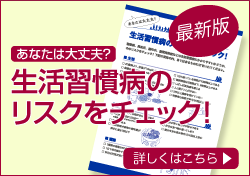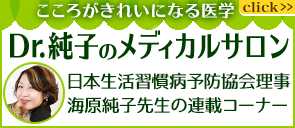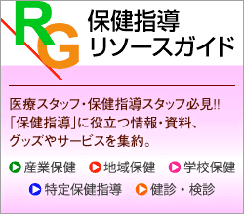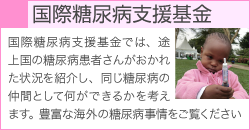飲酒
少酒の勧め
さまざまな生活習慣病がアルコールと密接に関わっていて、大酒をすれば多くの病気が誘発される可能性が高まります。「健康日本21」のなかでは、アルコールに関して「1日20g(日本酒に換算して一合程度)の摂取が望ましい」とされています。「百薬の長とはいへど、万の病は酒よりこそおこれ」という言葉もあるとおり、アルコールをたくさん飲める人でも、1日にその程度の飲酒量が望ましいということです。
●おもな酒類のアルコール量の目安
適正飲酒の10か条
公益社団法人アルコール健康医学協会では、アルコールの適正な飲み方・マナー等を以下の10か条にまとめています。
- 談笑し 楽しく飲むのが基本です
- 食べながら 適量範囲でゆっくりと
- 強い酒 薄めて飲むのがオススメです
- つくろうよ 週に二日は休肝日
- やめようよ きりなく長い飲み続け
- 許さない 他人(ひと)への無理強い・イッキ飲み
- アルコール 薬と一緒は危険です
- 飲まないで 妊娠中と授乳期は
- 飲酒後の運動・入浴 要注意
- 肝臓など 定期検査を忘れずに
多量飲酒によって生じる病気
過度の飲酒を長く続けると、さまざまな病気を引き起こす誘因となります。もっとも怖い病気が、最近、とくに問題になっているアルコール依存症です。
アルコール依存症は、大量のアルコールを長年にわたって飲み続けることで、アルコールを飲まずにいられなくなってしまう病です。体からアルコールが抜けると、イライラしたり、手の震えや発汗、動悸、頭痛、吐き気などの離脱症状が現れ、それを抑えるためにまた飲まずにいられなくなり、ついには精神的・身体的な影響のために仕事ができなくなるなど、生活面にも支障が出てきます。
アルコール依存症は「否認の病」とも言われ、本人は認めようとしない傾向があります。また、いったん飲酒をやめてもまた元の状態に戻ってしまうことも多いので、本人の強い意志と周囲のサポートがとても大切です。
アルコール依存症のほかに、アルコール性認知症という病気の心配もあります。これは、認知症の原因として、アルコールの多量摂取以外に考えられない場合に診断される病名です。
ただし、アルコールと認知症の関係はこの病名で診断される場合だけというわけではありません。例えば、アルコール摂取は脳血管障害のリスク因子であり、脳血管障害性認知症につながります。また認知症とは少し異なりますが、習慣的なアルコール摂取の影響でビタミンBが欠乏すると、ウェルニッケ脳症という病気になることがあります。つまり、アルコールの大量摂取は、さまざまな経路で脳にダメージを及ぼしかねないということです。
●我が国における疾病別の発症リスクと飲酒量(純アルコール量)
*喫煙習慣・飲酒習慣・食習慣・運動習慣・BMIから今後10年の「がん罹患リスク」を判断(国立がん研究センター 社会と健康研究センター)
厚生労働省では、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進を図るため、国民それぞれの状況に応じた適切な飲酒量・飲酒行動の判断に資する「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成し、2024年2月に公開しています。
厚生労働省は、本ガイドラインは、アルコール健康障害の発生を防止するため、国民一人ひとりがアルコールに関連する問題への関心と理解を深め、自らの予防に必要な注意を払って不適切な飲酒を減らすために活用されることを目的としており、「純アルコール量に着目しながら、自分にあった飲酒量を決めて、健康に配慮した飲酒を心がけることが大切です」と指摘しています。
飲酒に関する国内初のガイドライン(2024年2月)
数字で見る飲酒
10.9万人(入院7.5万人、外来3.4万人)。
1996年(21.7万人)をピークに減少
(健康日本21、厚生労働省)
さらに詳しく
- 一無、二少、三多で生活習慣病を予防
- みんなに知ってほしい飲酒のこと(厚生労働省)
- 健康づくり支援担当者のための総合情報サイト
- 公益社団法人アルコール健康医学協会
- アルコール健康障害に係る参考資料(厚生労働省)
- 科学的根拠に基づくがんリスク評価とがん予防ガイドライン提言に関する研究(国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト)
2019年11月 公開
2024年12月 更新