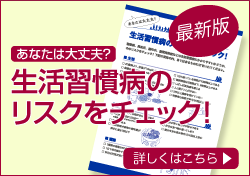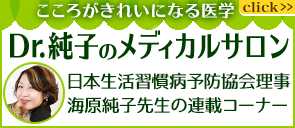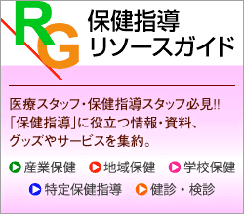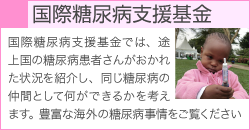2003年12月24日
糖尿病と関連が深い肥満や運動習慣などついて調査 厚生労働省平成14年 国民栄養調査結果の概況」より
カテゴリー: 糖尿病
厚生労働省が毎年行っている「国民栄養調査」の平成14年調査から、糖尿病に関係が深い項目をピックアップしてみましょう。まずは肥満者(BMI※25以上)の割合です。男性は 30〜60代の3割以上の人が肥満に該当し、70歳以上でも 26.3パーセントが肥満に該当します。女性の肥満者の割合は、40代までは 20パーセント以下ですが、50代で 25.6パーセント、60代で 33.3パーセント、70歳以上で 30.8パーセントとなっています。
性別にみると、男性については、20年前の昭和57年調査、10年前の平成4年調査、そして今回の調査と、年を追ってすべての年齢層で肥満者の割合が増えてきています。一方、女性は低体重(やせ)の割合が増えてきていて、20代で 26.0パーセント、30代で15.1パーセントがやせに該当し、20年前に比べてそれぞれ2倍に増えています。しかも、実際には太っていないのに太っていると思っていたり、やせているのにもかかわらず体重を減らそうとしている女性が少なくないことがわかりました。
ストレスと食事量の変化についてみてみましょう。男性・女性ともにストレスを感じたときも食事量は変わらないと答えた人が一番多いという結果が出ていますが、その割合は男性 56.5パーセントに対し、女性 38.0パーセントで、ストレス時に女性は男性よりも食事量が変わりやすい傾向がうかがえます。とくに、食事量が多くなると答え人の割合は、男性 6.8パーセントに対し女性17.9パーセントと、性差が現れています。
運動習慣については、男性 31.6パーセント、女性 28.3パーセントが運動を習慣としていることがわかりました。年齢別では、20代17.0パーセント、30代19.1パーセント、40代 22.4パーセント、50代 29.9パーセント、60代 40.8パーセント、70歳以上 35.4パーセントで、若年者層ほど運動習慣が少ないという結果になっています。
※BMI:Body mass index(ボティー・マス・インデックス)の略で、肥満や低体重(やせ)の判定に用いられる数値です。BMIは、体重 (kg) ÷ 身長 (m) ÷ 身長 (m) によって算出します。25 以上は肥満、18.5 未満はやせと判定されます。BMI22 が理想体重です。