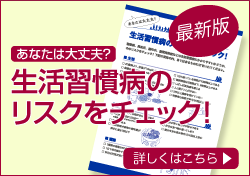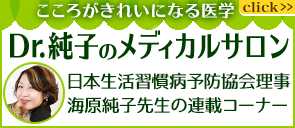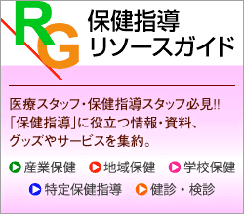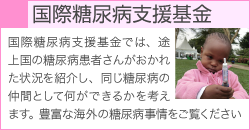2022年11月18日
重要性を増す街中の「ゆびさきセルフ(検体)測定室」の役割! ~検体測定室連絡協議会「世界糖尿病デー・健康啓発セミナー2022」~
キーワード: 生活習慣 脂質異常症(高脂血症) 糖尿病 協会・賛助会員関連ニュース
 今年も11月14日の世界糖尿病デーにあわせて、検体測定室連絡協議会による「世界糖尿病デー・健康啓発セミナー」が、11月2日(水)に東京大学鉄門記念講堂にて開催されました。当セミナーには、日本生活習慣病予防協会も後援団体として参加しており、当協会の吉田 博専務理事の講演も行われました。
開催に先立ち、検体測定室連携協議会執行委員長で筑波大学内分泌代謝・糖尿病内科准教授の矢作直也氏が検体測定室の現状を報告しました。
検体測定室(ゆびさきセルフ測定室)の件数は、新型コロナウイルス感染症パンデミック以降にやや動きが鈍っているものの、国内に約2,000件を数えること、その一方で地域差があり一桁台の県も数県あるとのことです。続いて、検体測定室ガイドラインやPHR(パーソナルヘルスレコード)、動脈硬化性疾患予防ガイドライン最新版をテーマとする講演と、パネルディスカッションが行われました。
今回のセミナーは、検体測定室の「受診勧奨」という役割の重要性が増し、PHRやオンライン診療との連携などによって、地域の健康ステーションとしての将来像が期待される内容でした。本レポートでは、各講演のハイライトを紹介します。
今年も11月14日の世界糖尿病デーにあわせて、検体測定室連絡協議会による「世界糖尿病デー・健康啓発セミナー」が、11月2日(水)に東京大学鉄門記念講堂にて開催されました。当セミナーには、日本生活習慣病予防協会も後援団体として参加しており、当協会の吉田 博専務理事の講演も行われました。
開催に先立ち、検体測定室連携協議会執行委員長で筑波大学内分泌代謝・糖尿病内科准教授の矢作直也氏が検体測定室の現状を報告しました。
検体測定室(ゆびさきセルフ測定室)の件数は、新型コロナウイルス感染症パンデミック以降にやや動きが鈍っているものの、国内に約2,000件を数えること、その一方で地域差があり一桁台の県も数県あるとのことです。続いて、検体測定室ガイドラインやPHR(パーソナルヘルスレコード)、動脈硬化性疾患予防ガイドライン最新版をテーマとする講演と、パネルディスカッションが行われました。
今回のセミナーは、検体測定室の「受診勧奨」という役割の重要性が増し、PHRやオンライン診療との連携などによって、地域の健康ステーションとしての将来像が期待される内容でした。本レポートでは、各講演のハイライトを紹介します。
検体測定室ガイドラインについて
厚生労働省医政局地域医療計画課医療関連サービス室 室長補佐畠 伸策 氏
最初の講演は、検体測定室のガイドラインの概要を厚労省の畠氏が紹介。検体測定室では、検体は受検者自身が採取・採血し、測定項目は決められたものの範囲内に限ること、結果に基づいた診断はせずに受診勧奨を励行すること、物品購入を勧奨しないことなどの原則が解説されました。
同氏は、検体測定室の件数を人口10万人当たりに換算して都道府県別に示したデータを紹介。それによると、石川、岩手などは10を超えているのに対して、福井や島根など、1未満の県も複数あるとのことです。
検査項目の測定状況としては、血糖や脂質関連指標がよく測定されていて、一方で肝機能関連指標はあまり測定されていないことが示されました。2021年(令和4年)8月末時点のデータでは、HbA1cは全測定検査室の83.4%が測定、中性脂肪は73.7%、HDL(善玉)コレステロールが73.2%、LDL(悪玉)コレステロールが69.8%、血糖値が61.2%、それぞれ測定されていました。しかし、肝機能関連検査のASTは5.3%、ALTやγ-GTPは4.9%という結果でした。
またガイドラインで定める事項で、年1回以上の外部精度管理の参加が18%、精度管理台帳の作成5%、作業日誌の記録4%に未実施が確認され、今後の改善が待たれます。
Smart One Healthと検体測定室
株式会社インテグリティ・ヘルスケア 代表取締役会長医療法人社団 鉄祐会 理事長 武藤 真祐 氏
武藤氏は、東京都内と宮城県石巻市で主に在宅医療を行う医療法人の理事長で、PHRのプラットフォームなど提供している企業を経営しています。
同氏は、自らの経験から開発したPHRとオンライン診療の機能を併せ持つSmart One Healthの全体像を概説しました。患者さんの健康データを医師と患者さんが共有することによって、オンライン診療がスムーズになり、患者さんの利便性が向上して、受診中断の抑止にもつながるなどの効果が期待できるとPHR導入のメリットを紹介しました。
薬局との連携についても、PHRを基に服薬指導の効率化が図られ、また、検体測定室での精度の高い検査結果を基点として患者さんと薬局の新たな接点を生み出すというメリットが期待できるとし、「デジタル情報の活用によって、日本国内の薬局を『地域の健康ステーション化』することが可能ではないか。そのために、Smart One Healthと検体測定室の連携を進めていきたい」と、今後の抱負を語りました。
脂質検査の重要性と動脈硬化学会の新ガイドライン動向
東京慈恵会医科大学附属柏病院 病院長臨床検査医学講座 教授 吉田 博 氏
講演の3題目は、今年改訂された「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」について、東京慈恵会医科大学附属柏病院病院長の吉田博氏により改訂ポイントの解説が行われました。
今回の改訂のポイントは、従来は空腹時採血値のみしか示されていなかった診断基準値について、中性脂肪(TG)に関しては随時採血の基準値も別途掲げられたことが大きいということです。
総コレステロール(TC)は食前と食後で変化がないのに比べて、TGは食後に高くなり、近年では食後(随時)TG高値が心血管疾患の独立したリスク因子であることが明確になってきています。そこで今改訂から、随時採血175mg/dLという基準値が設けられました。
吉田氏は、一般的に健診の際は他の検査項目との対応から原則的に空腹時に採血することが多いため、「随時であることが多い検体測定室においては、随時採血のTG値に基づき受診勧奨につなげることの意義が今後より重要になる」と語りました。
糖尿病の患者さんは、高TG血症を併発していることが多く、「世界糖尿病デー」にあわせて開催された本セミナーの趣旨からも、強調されるポイントと言えそうです。
ガイドライン改訂のその他のポイントとしては、リスク評価に冠動脈疾患だけでなく、アテローム性脳梗塞も取り入れたこと、そのために久山町研究のデータを用いること、家族性高コレステロール血症のより積極的な診断を可能とし、今後の保険医療承認も期待されるエコーによるアキレス腱肥厚度測定の基準値が定められたことなどが紹介されました。
また、診断基準値以外にも、Lp(a)、small dense LDL-Cなどへの留意が必要で、とくに後者は「超悪玉コレステロール」と呼ばれていて、糖尿病患者では高TG血症に伴い高値になりやすいことなどが解説されました。
パネルディスカッション「これからの検体測定室」
上記3題の講演に続いて、健康サポート薬局での豊富な経験を持つ田辺薬局株式会社の長井彰子氏が加わり、「これからの検体測定室」をテーマとするパネルディスカッションが開催されました。
前半は、司会の矢作氏と各パネルストとの間での質疑応答。まず畠氏は、「人口あたりの検体測定室が最も多い岩手や石川が10人あたり10件とのことなので、ほぼ1万人に1件が理想的と考えられるか」との矢作氏の質問に対して、「10万人に1件でも、ふつうに生活している限りあまり目に入らない。もっと認知度を高めていく必要があるのではないか」と今後への期待を述べました。
続いて武藤氏は、現状では日常診療にPHRが十分活用されていないのではないかとの指摘があることについて「そのとおり」と述べたうえで、その理由として、患者さんの側には各種検査値の入力の手間やそれを医師に提示するハードルがあり、医師側にも患者さんが提示するスマホを操作することにハードルがあることなどを挙げ、それらのデータを一元化して共有し、患者さんが他院を受診した際にも共有できることのメリットを改めて強調しました。
次に吉田氏は、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」改訂が検体測定室に及ぼすインパクトについて2点を補足。その一つは診断基準に随時採血値が設けられたことで、「検体測定室を訪れる方はほぼ食後の状態だと思われる。その方々の中から食後高TG血症の人が見つかるのではないか。それによって検体測定室が受診への動機づけの場になることが期待できる」とのことです。もう一つは、患者数は多いと推定されるにも関わらず、現状で未診断の人が少なくなく、心筋梗塞リスクの高い家族性高コレステロール血症(ヘテロ型)の患者さんの受診の動機づけ、予防のための機会になるのではないかとの期待です。
長井氏は、まず、今年度から始まったリフィル処方箋(反復利用できる処方箋)の検体測定室への影響について、「医師の診療間隔が延びると考えられ、その間の状態を確認する一つのツールになるのではないか」と見通しを語りました。同様に、今後オンライン診療が普及した場合、採血検査の間隔がこれまでよりも開くと予測されることからも、検体測定室が活用されるケースがあり得るとのことです。
また、同氏は「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」改訂に関連して、「血糖関連指標に加えて脂質関連でも随時に測定すべき検査値が示されたことで、検体測定室を利用していただく意義がより向上したと思う」とのコメントを述べています。
最後にフロアーから、検体測定室が国民にあまり知られていないのではないかとのコメント、受診勧奨を行う際の医療機関のリストが作れない薬局も多いが、オンライン診療と連携が取れるのかとの質問があり、矢作氏は、検体測定連携協議会でも認知向上のための施策は引き続き図っていきたいこと、検体測定室など薬局と医療機関の地域医療連携に、オンライン診療も組み込まれていくのではないかと語り、パネルディスカッションは終了しました。
 ゆびさきセルフ測定室は、検査を受ける人が、指先から自分で採取した血液から、血糖値やHbA1c、中性脂肪など生活習慣病に関する項目を検査できるスペースです。
測定の説明から結果の説明まで、20~30分で正確に測定できることが話題となり、全国の調剤薬局などで設置店が増え続けています。
ゆびさきセルフ測定室は、検査を受ける人が、指先から自分で採取した血液から、血糖値やHbA1c、中性脂肪など生活習慣病に関する項目を検査できるスペースです。
測定の説明から結果の説明まで、20~30分で正確に測定できることが話題となり、全国の調剤薬局などで設置店が増え続けています。
一般社団法人 日本生活習慣病予防協会