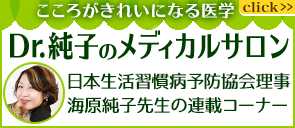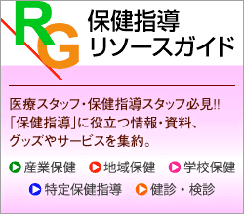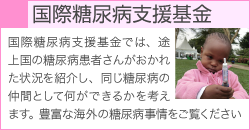2024年07月18日
運動不足による疾患リスクを抱えている人が世界に18億人 WHO報告 ~無理な目標は立てずに、まずは歩くことからはじめよう!(『一無、二少、三多』-多動より)
キーワード: 生活習慣 一無・二少・三多 「多動」身体を活発に動かす 全国生活習慣病予防月間 協会・賛助会員関連ニュース 厚生労働省の調査 身体活動・運動不足
 世界で18億人近くの人が、運動不足による疾患リスクを抱えているとするデータが2024年6月世界保健機関(WHO)のニュースリリースに掲載されました。本データは「The Lancet Global Health」に掲載された研究論文に基づくものです1)。
世界で18億人近くの人が、運動不足による疾患リスクを抱えているとするデータが2024年6月世界保健機関(WHO)のニュースリリースに掲載されました。本データは「The Lancet Global Health」に掲載された研究論文に基づくものです1)。公表されたデータによると、2022年には世界中の成人のほぼ3分の1に相当する31.3%、約18億人が、推奨される身体活動レベルを満たしていないとのことです。また、この割合は2010年から約5ポイント増加し、この増加傾向が続くと、運動不足に該当する人の割合は2030年までに35%に達すると予測されています。
日本生活習慣病予防協会(監修:代表 和田 高士)
アジア太平洋地域、南アジアで運動不足の人の割合が高い
地域別にみると、高所得のアジア太平洋地域(48%)、および南アジア(45%)でとくに運動不足の人の割合が高値となっています。また、性別で比較した場合、男性(29%)よりも女性(34%)で運動不足の割合が高く、国によってはこの差が20ポイントにも達するとしています。
WHO事務局長のTedros Adhanom Ghebreyesus氏は、「我々は、この憂慮すべき傾向を逆転させる政策強化や資金増額を含む、大胆な行動の優先化への決意を新たにしなければならない」と、ニュースリリースに記しています。なお、WHOは、成人が1週間あたり中程度の運動を150分、または高強度の運動を75分、行うことを推奨しています2)。
一方、一部の国では改善の兆しが見られるようです。22カ国(欧州の高所得西側諸国12カ国、オセアニア4カ国、サハラ以南アフリカ6カ国)では運動不足者の減少が認められ、これらの国でこの傾向が続けば、「2030年までに身体活動不足の割合を15%削減する」というWHOの目標3)を達成する可能性が高いとの予測が述べられています。
わが国の運動の現状と対策
わが国は、WHOの報告による運動不足が増えている高所得のアジア太平洋地域に属します。
健康日本21第二次(2013~2023年、厚生労働省)では、運動に関して「日常生活における歩数の増加」と「運動習慣者(1回3 分以上の運動を週2回以上実施し、年以上継続している人)の割合の増加」が設定されていましたが、最終評価判定は「C(変化なし)」でした4)。
健康日本21第二次では「運動やスポーツを習慣的に⾏っていない⼦どもの割合の減少」も調査されています。その結果をでは、ベースラインの2010年より2014年ごろまでは割合の急激な低下傾向がみられますが、以降は運動習慣のない子供が徐々に増えている傾向を示しています4)。
また、スポーツ庁が実施している「わが国のスポーツの実施状況に関する世論調査*(令和5〔2023〕年度)」5)では、20歳以上の週1日以上の運動・スポーツ実施率は、52.0%(前年度から0.3ポイント減)。男女別では、男性が54.7%(前年度から0.3ポイント増)、女性が49.4%(前年度から0.8ポイント減)となっており、男性より女性の運動・スポーツ実施率が低い結果でした。
年代別では、20~50代の働く世代で低い傾向が続いています。さらに、週1日以上のスポーツ実施率は、20~50代の働く世代で男女差が拡がっており、男性では前年度を上回ったのに対し(50代は前年度と同じ)、女性は前年度を下回っています。
運動・スポーツの実施頻度が減ったあるいは増やせない理由としては、「仕事や家事が忙しいから」が37.2%と最も多く、「面倒くさいから」が27.4%と続いています。そして「現在運動・スポーツはしておらず今後もするつもりはない」と答えた無関心層の割合は17.6%と前年度から1.0ポイント増加していました。
*本調査は昭和54(1979)年度から概ね3年ごとに実施してきた「体力・スポーツに関する世論調査」(平成27〔2015〕年度のみ「東京オリンピック・パラリンピックに関する世論調査」)を踏襲するものです。調査方法は平成28〔2016〕年度より調査員による個別面接聴取(サンプル数3,000人)からwebアンケート調査(対象は令和3〔2021〕年度まで20,000人し、令和4〔2022〕年度以降40,000人)に変更されています。
運動不足解消も『一無、二少、三多』で!
 日本生活習慣病予防協会では、健康標語『一無、二少、三多』(無煙・禁煙、少食、少酒、多動、多休、多接)を推奨しています。
日本生活習慣病予防協会では、健康標語『一無、二少、三多』(無煙・禁煙、少食、少酒、多動、多休、多接)を推奨しています。
運動不足では消費エネルギーが少ないために、肥満、とくに内臓脂肪型肥満が起きやすく、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの肥満に伴う病気(メタボリックシンドローム)のリスクが高まります。さらに筋力の低下、筋肉量の減少、あるいは関節の可動性が減って、ロコモティブシンドロームやサルコペニアなどの運動器疾患が生じやすくなります6)。
厚生労働省の「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」では、身体活動不足の人に、1日の歩数や運動量の大目標を立ててもなかなか達成できないため、『+10(プラステン):今より10分多く体を動かそう』を推奨しています7)。
日常生活の中で身体活動量を増やしましょう。座りっぱなしは避け、身体活動をできるだけ多くして、しっかり毎日の生活の中で維持しましょう。「2本の足は2人の医者」という格言があります。まずは、無理な目標はたてずに、良く歩くことから始めましょう6)。
一無、二少、三多とは関連情報
1) WHO News/Nearly 1.8 billion adults at risk of disease from not doing enough physical activityStudy:Lancet Glob Health. 2024 Jun 25:S2214-109X(24)00150-5
2) WHO運動・身体活動および座位行動に関するガイドライン(日本語版)
3) 身体活動に関する世界行動計画2018-2030(GAPPA)(厚生労働省 e-ヘルスネット)
4) 健康日本21で日本人はどのくらい健康になった?(日本生活習慣病予防協会)
5) 令和5年度スポーツの実施状況等に関する世論調査(スポーツ庁)
6) 生活習慣病とその予防―身体活動・運動不足(日本生活習慣病予防協会)
7) アクティブガイド(厚生労働省)