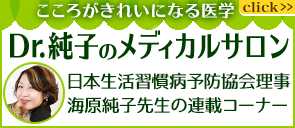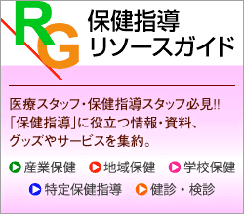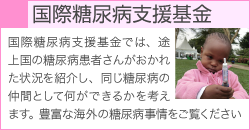2019年06月21日
高尿酸血症のリスクは痛風だけではなかった! 中高年だけでなく、若い世代から気をつけたい尿酸値
キーワード: 高血圧 脂質異常症(高脂血症) 糖尿病 CKD(慢性腎臓病) 高尿酸血症/痛風 肥満症/メタボリックシンドローム 動脈硬化 食生活
尿酸値が高いほど痛風になりやすいことは、よく知られている。痛風の患者数は、年々増えて推定約110万人。さらに「尿酸値が高めだけれども症状が出ない人」は1,000万人を超えるという。最近の研究では、尿酸値が基準値を超える「高尿酸血症」を放置すると、痛風だけでなく、メタボリックシンドロームや尿路結石、腎障害、脳・心血管障害の危険因子となる可能性も指摘されている。
そんな中、2018年12月に8年ぶりの改訂となる「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版」が出され、今月(2019年6月)にはそのダイジェスト・ポケット版が刊行される。尿酸値が高めの人はどんなリスクに注意して、どのような対策を取るとよいのか。
今回は、本ガイドラインの改訂副委員長で、ダイジェスト版の監修を担当された市田公美先生(東京薬科大学 薬学部 教授)、同改訂委員でプリン体測定の第一人者である金子希代子先生(帝京大学 薬学部 教授)にお話を伺った。また、一般社団法人 日本生活習慣病予防協会の宮崎滋理事長には、同協会の生活習慣病予防に対する取り組みについてご紹介いただいた。
そんな中、2018年12月に8年ぶりの改訂となる「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン 第3版」が出され、今月(2019年6月)にはそのダイジェスト・ポケット版が刊行される。尿酸値が高めの人はどんなリスクに注意して、どのような対策を取るとよいのか。
今回は、本ガイドラインの改訂副委員長で、ダイジェスト版の監修を担当された市田公美先生(東京薬科大学 薬学部 教授)、同改訂委員でプリン体測定の第一人者である金子希代子先生(帝京大学 薬学部 教授)にお話を伺った。また、一般社団法人 日本生活習慣病予防協会の宮崎滋理事長には、同協会の生活習慣病予防に対する取り組みについてご紹介いただいた。
高尿酸血症と推定される人が、1,000万人を超える

高尿酸血症が増加している要因としては、食生活、とくにお酒の飲みすぎやプリン体の多い食物や果糖(甘いジュースなど)の過剰摂取、そして運動不足による肥満がベースにあるという。そして「メタボリックシンドロームの人は明らかに尿酸値が高く、明確な相関関係があることがわかっています」(市田先生)
高尿酸血症の発症メカニズム

プリン体から作られた尿酸は、約2/3は腎臓から、約1/3は腸管から排泄される仕組みになっている。この産生と排泄のバランスが崩れると、尿酸が体内に溜まっていく。血液中の尿酸が7.0mg/dLを超えると「高尿酸血症」と呼ばれる状態になり、痛風発作や尿路結石などを引き起こす可能性が高まる。
高尿酸血症には、プリン体の過剰摂取による「尿酸産生過剰型」と、腎機能低下による「尿酸排泄低下型」、またはその混合したタイプがあるが、最新のガイドラインでは、腸からの尿酸の排泄が悪くなる「腎外排泄低下型」がもう1つのタイプとして追加された。日本人の痛風患者では、約8割が尿酸排泄低下型か混合型と考えられている。
|
尿酸値の正常値は?
ガイドラインでは、7.0mg/dLを正常値の上限とし、これを超えるものを高尿酸血症と定義している。女性の場合は、女性ホルモンが尿酸の腎臓からの排出を促進するため、平均値が男性よりも1.5 mg/dLぐらい低くなる。閉経後は徐々に数値が上がる傾向にあるが、閉経前で、尿酸値が5.5 mg/dLを超えたら、生活習慣病のリスクに注意が必要とする専門家もいる。 |
プリン体はうまみのもと、おいしいものには多く含まれる
プリン体は、食べ物から摂取するものと体内で自然に作られるものとに分けられる。体内で作られる食事由来のプリン体は全体の2割に過ぎないが、過剰摂取は高尿酸血症を招く。また、プリン体はうまみ成分でもあり、おいしいものに多く含まれる。「プリン体のうまみ成分は呈味性ヌクレオチドと呼ばれ、イノシン酸(カツオ節や肉のおいしさのもと)、グアニル酸(干しシイタケに含まれる)、キサンチル酸(酵母に含まれる)などが含まれています。一番多いのはレバーや白子といった内臓。アルコールでは、ビールに多く含まれます。ただし、アルコールはそれ自体が尿酸値を上げる作用を持つので、種類を問わず飲む量にも注意が必要です」(金子先生)
新たにガイドラインに追加された高尿酸血症のリスクとは?
高尿酸血症のリスクでは、痛風と尿路結石が知られているが、ほかにも様々な病気との関連性が明らかになってきた。「今回のガイドラインで明らかになってきたのが腎障害。以前から腎障害を促進する可能性が指摘されていたが、腎障害を有する高尿酸血症患者に尿酸値を下げる薬(尿酸降下薬)を投与すると、腎障害の進行を遅らせることができるというエビデンスが得られています」と市田先生。
尿酸値が高い人では、肥満やメタボリックシンドロームを伴うことも多い。さらに、まだ観察中ということだが、脂質異常症、高血圧などの生活習慣病との関連も指摘されており、その結果、脳・心血管障害の促進因子になっている可能性も考えられるという。こうした理由から、市田先生は「痛風がなくとも、ほかの検査数値同様に尿酸値を気にかけ、肥満解消や尿酸値を下げるような生活習慣を取り入れること。そして、生活習慣の改善を試みても数値が高いようなら、かかりつけ医の受診が勧められる」とアドバイスする。
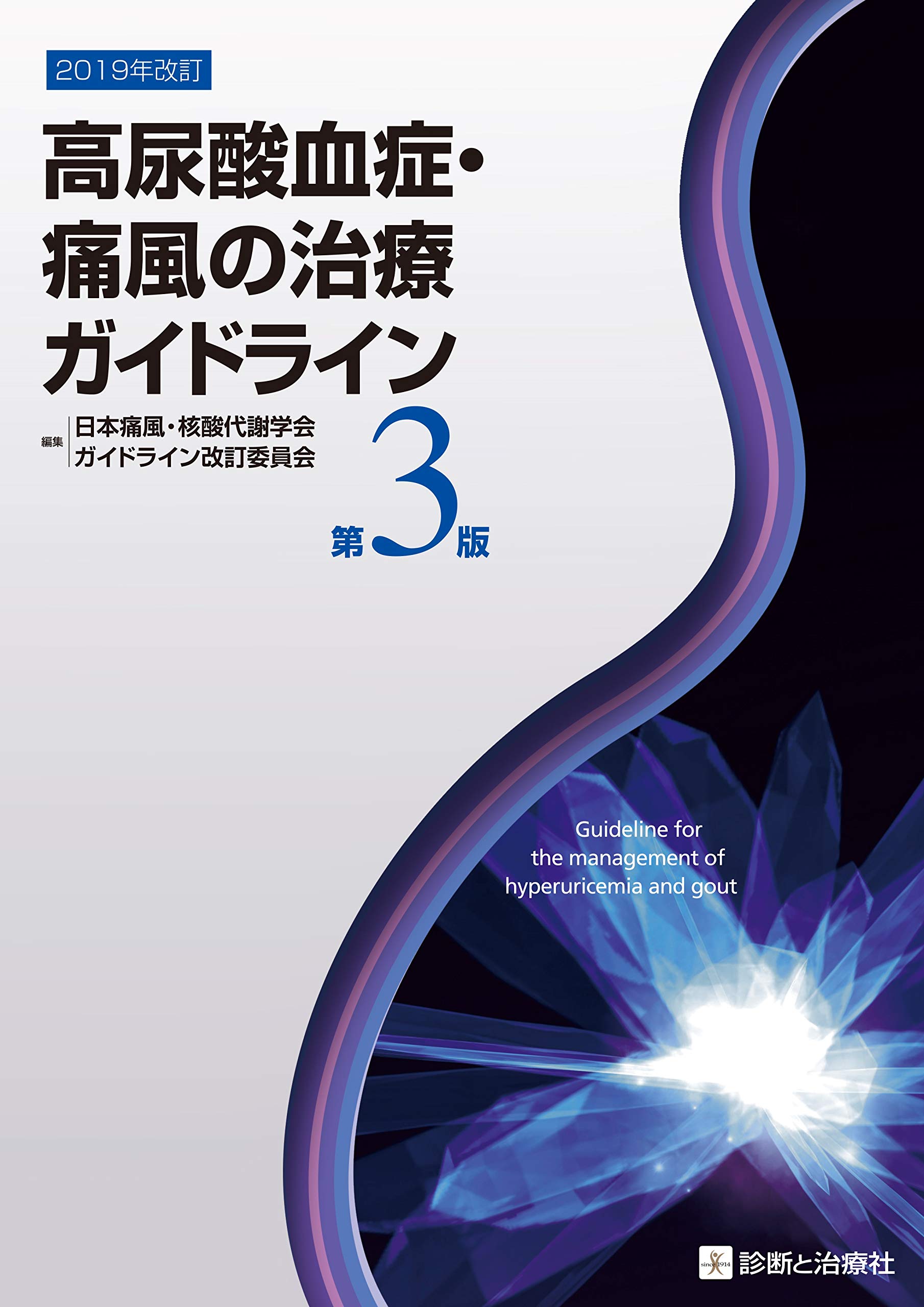
新ガイドラインでは、高尿酸血症における腎障害のリスクや病型分類のあらたな考え方、クリニカルクエスチョンなどが追記されたほか、より具体的な治療アルゴリズムなども紹介されている。 「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン第3版 ダイジェスト・ポケット版」は6月末に発売される。 |
尿酸値が高めの方に、生活習慣改善のポイント
「尿酸値が高め」と指摘されたら、生活習慣の改善を始めよう。そのポイントは次の5つである。
| ● アルコールの過剰摂取に注意 |
| ● プリン体の多い食物を摂りすぎない |
| ● 腹八分目、食べすぎない、適正体重を心がける |
| ● 水分を十分に摂る |
| ● 運動、とくに有酸素運動を心がける |
飲酒は、20〜25g/日以下が適量とされている。ビール500mL、日本酒1号、ワインなら1グラス、ウイスキーダブル1杯、焼酎では90mL程度を目安に、休肝日を取ることも心がける。ビールのプリン体は尿酸になりやすく、体内に吸収されやすい。対して、ワインには、尿酸排出作用が期待できるポリフェノールが含まれている。ただし、アルコールそのものに尿酸の排出をブロックする作用があるため、ワインであっても、「プリン体ゼロ」と表示しているアルコール飲料であっても、飲み過ぎには注意したい。 ● プリン体の多い食物を摂りすぎない
ガイドラインでは、プリン体の摂取量を1日400mgに抑えることが推奨されている。金子先生のアドバイスは、「プリン体含有量の多い食品は1回の食事で50g程度にして、3食のうち1食でも、海藻類、野菜、大豆製品、卵などプリン体が少なめの食材を中心とした食事を選択すると、摂り過ぎを防ぎ、かつ栄養バランスも良くなるでしょう。意外かもしれませんが乳製品もお勧めです。牛乳やヨーグルトといった乳製品はプリン体が少なく、乳タンパク質のカゼインに尿酸の排泄を働きがあるためです」 [食品中のプリン体量](食品100gあたりに含まれるプリン体量)
|
きわめて多い (300mg〜) | 鶏レバー、干物(マイワシ)、白子(イサキ、ふぐ、たら)、あんこう(肝酒蒸し)、太刀魚、健康食品(DNA/RNA、ビール酵母、クロレラ、スピルリナ、ローヤルゼリー)など |
| 多い (200〜300mg) | 豚レバー、牛レバー、カツオ、マイワシ、大正エビ、オキアミ、干物(マアジ、サンマ)など |
| 中程度 (100〜200mg) | 肉(豚・牛・鶏)類の多くの部位や魚類など ほうれんそう(芽)、ブロッコリースプラウト |
| 少ない (50〜100mg) | 肉類の一部(豚・牛・羊)、魚類の一部、加工肉類など ほうれんそう(葉)、カリフラワー |
| きわめて少ない (〜50mg) | 野菜類全般、米などの穀類、卵(鶏・うずら)、乳製品、豆類、きのこ類、豆腐、加工食品など |
(提供:帝京大学 薬学部 臨床分析学研究室) 尿酸値を下げやすい食品成分としては、タンパク質、ビタミンC、ポリフェノール、フラボノイド、食物繊維が報告されている。乳製品やコーヒーの摂取量が多い人ほど尿酸値が低いという疫学調査の報告もある。また、ヨーグルト・納豆などの発酵食品は、腸内環境を整えるという意味でも勧められる食材である。 帝京大学 薬学部 臨床分析学研究室では「プリン体計測プログラム」を公開している。アンケートに答えるだけで、無料で利用できる。
https://teikyo.purine-lab.com/purine/ ● 腹八分目、食べすぎない、適正体重を心がける
血清尿酸値が高いほど、メタボリックシンドロームの頻度が高く、内臓脂肪が蓄積している人ほど、血清尿酸値が高くなるという研究報告があり、肥満と尿酸値は互いに強い関連性があることがわかってきた。つまり、肥満を解消することで、尿酸値の改善も期待できるのだ。食事は腹八分目にしてバランスのよい食事と適度な運動を取り入れ、適性体重を維持するよう心がけよう。 ● 水分を十分に摂る(果糖を多く含む甘味飲料は控える)
尿酸の排出を促すために、水分をとり十分な尿量を確保しよう。ただし、果糖や砂糖の多いジュースなどを摂りすぎないよう注意したい。「砂糖入り飲料を1日に2回以上飲む人の痛風発症リスクは、2日に1回以下の人と比べて1.9倍になるという報告があります。また、果糖の過剰摂取はメタボリックシンドロームや尿路結石の促進とも関連しています」(金子先生) ● 運動、とくに有酸素運動を心がける
運動は、尿酸値を下げるだけでなく、生活習慣病全般にわたり有効な改善効果が期待できる。具体的には、歩く,水泳,ジョギングなどで脈がやや速くなる程度の有酸素運動が推奨される。ただし、激しい運動は一時的に尿酸値を上げてしまうといわれている。何らかの病気のある人はかかりつけ医に相談して、適切な運動を行うようにしよう。
日本生活習慣病予防協会の取り組み
最後に、長らく、健康診断の推進に携わり、肥満症の専門医でもある宮崎 滋先生に日本生活習慣病予防協会の取り組みについて伺った。「腹八分目の食生活と適度な運動で肥満に気をつけること、お酒の飲みすぎないことは、生活習慣病すべてに共通すること。健康で楽しく、長く生きるために、できるだけ病気にならない、できるだけ薬に頼らない生活習慣を身につけるべきです」。「日本生活習慣病予防協会では、一無(禁煙)、二少(少食、少酒)、三多〔多動(身体を動かす)、多休(ゆっくり休養する)、多接(多様なつながり)〕を健康スローガンに生活習慣病を予防するために、ホームページを通して、さまざまな啓発活動を行っています。当協会のホームページにもぜひお立ち寄りください」
(取材・文/及川夕子)
[mhlab]